こんにちは。
最近、ChatGPTやGeminiなど、AIの進化ってすごいですね。
私も、仕事やプライベートでよく使ってます。
でも、「いつか自分の仕事がAIに奪われるんじゃないか」、そんな不安を感じてしまうこともあります。
特に、これからプログラミングを勉強しようとしている方や、IT企業でやっと仕事を覚えた方は、これからのスキルアップやキャリアを考える上で大きな問題です。
しかし、結論から言えば、ITエンジニアの仕事はなくなりません。
今回は、AIによってITエンジニアの役割がどう変化するのか、そして、これからの時代で「必要とされ続けるITエンジニア」なるには何をするべきかを、具体的に解説していきます。
なぜ「ITエンジニア不要論」が語られるのか?
ITエンジニアの仕事は、大きく分けると以下の3つになります。
- 設計
- 製造
- 試験
特に時間がかかるのが、2.製造と3.テストになります。
2.製造と3.テストがITエンジニアの腕の見せどころになります。
それに対して、AIが得意な作業は、単純なコード生成、言語変換、バグ修正などです。
つまり、ITエンジニアの仕事と重なるところが多いのです。
また、AIは、ITエンジニアが作るデザインよりもモダンなデザインを生成できます。
これまでは、Webデザイナーに作成してもらっていました。
そして、その生成は、私たちITエンジニアが行うより遥かに早いのです。
そのため、AIが発展すると、「ITエンジニアは不要になる」と考える人も出てくるのです。
それでもITエンジニアが必要な理由 ― AIにはできない「本質的な仕事」
しかし、AIにはできない、私たちITエンジニアにしかできない「本質的な仕事」があります。
AIの限界と、人間の価値
AIは、デザインや単純なコードを生成することができます。
しかし、生成したデザインや単純なコードに対して「責任」を取ることはできません。
つまり、「AIは優秀な『作業者』になることはできても、『責任者』にはなれない」のです。
私たちITエンジニアは、開発したシステムに対して、責任があります。
人間にしかできないこと
私たちITエンジニアには、「責任」以外にも以下のような役割があります。
- 課題の発見と定義
- システムの設計
- 品質の担保と最終責任
ITエンジニアは、顧客の問題の本質を理解し、システム要件に翻訳する仕事があります。
ときには、顧客自身が問題の本質に気づいていない場合もあります。
ITエンジニアは、問題の本質を顧客から聞き出し、解決策をシステム要件に組み込むのです。
また、ITエンジニアは、拡張性、保守性、コストを考えた最適な設計を行う必要があります。
いくら動作するシステムでも、拡張性、保守性の悪いシステムでは、リリース後の機能の追加が難しいシステムでは、結局、コストが高くなってしまいます。
そして、最後に、ITエンジニアは、作成したシステムの品質の担保と最終責任を負うのです。
これらの役割は、AIにはできませんよね。
これからのITエンジニアの新常識:「AIは史上最高の相棒である」
では、これからのITエンジニアは、どのように変化するのでしょうか。
意識の転換
要件定義の整理やドキュメントの作成は、AIが得意とする分野です。
また、製造と試験は、AIで行うことが可能となっています。
ただ、AIで生成したコードは、拡張性、透明性が欠けている場合があるので注意が必要です。
その他にも、打ち合わせの音源から仕様の作成、要件定義を作成することも、ある程度できます。
ただし、打ち合わせの内容には、暗黙の了解が含まれていませんので追加する必要があります。
つまり、AIでITエンジニアの作業を行うことは可能ですが、どうしてもAIだけでは顧客がのぞむシステムは作れないのです。
なので、AIは「面倒な作業を肩代わりしてくれる超優秀なアシスタント」として使用するといいのです。
新しいITエンジニア像
上記の内容からすると、AIが発展すれば、そのうちITエンジニアは不要になるのではないかと不安になってきますね。
しかし、ITエンジニアは不要にはなりません。
電卓の登場で数学者が不要にならなかったように、AIの登場でITエンジニアは、より創造的な仕事に集中できるようになるのです。
具体的には、以下になります。
- 仕様・要件定義の作成:
- 大枠は、AIが作成してくれます。
ITエンジニアは、不足している内容を追記します。 - 設計:
- 大枠は、AIが作成してくれます。
ITエンジニアは、拡張性、透明性を考え修正が必要です。 - 製造:
- 大枠は、AIが作成してくれます。
ITエンジニアは、設計にそった製造になっているか確認が必要です。 - 試験:
-
試験仕様書は、仕様書や設計書をもとにAIが作成してくれます。
ITエンジニアは、漏れがないかの確認が必要です。
実施も、AIを使用 して行うことが可能です。
しかし、最終的な動作確認はITエンジニアが行う必要があります。
つまり、ITエンジニアは、「車の運転手」ではなく、「どの道を行くかを決めるナビゲータ兼整備士」のような存在になるのです。
【行動計画】AI時代を生き抜くために、私たちが今から身につけるべき5つのスキル
では、私たちITエンジニアは、何をすればいいのでしょうか?
結論を言うと、以下5つのスキルを磨く必要があります。
- 課題設定能力
- システムデザイン能力
- AI活用能力
- 品質保証・倫理観
- コミュニケーション能力
課題設定能力
打ち合わせの内容から、仕様の作成や要件定義は、AIが作成することができます。
しかし、話の裏にある、本当の課題については、私たちITエンジニアが理解し、仕様や要件に取り込む必要があります。
システムデザイン能力
ITエンジニアは、プログラミングだけでなく、その周辺技術(クラウド、DBなど)にも視野を広げる必要があります。
システムアーキテクチャという能力ですね。
プログラミングも、拡張性、透明性のよいものに修正できるようになる必要があります。
AI活用能力
いろんなAIを積極的に使い、うまくプロンプト(指示出し)を作成できるように練習する必要があります。
AIも得意・不得意があるので、どのAIを使うかを選択できるようになる必要があります。
プロンプトについては、Tipsも多く出ているので、調べておくのもいいですね。
品質保証・倫理観
上にも書いたのですが、AIは品質を保証することはできません。
なので、私たちITエンジニアが補完する必要があります。
また、AIには、倫理観が欠如しているものがあります。
なので、私たちITエンジニアが倫理的に問題ないかを確認する必要があります。
コミュニケーション能力
顧客やメンバーと開発するシステムについて話をするのは、ITエンジニアです。
なので、コミュニケーション能力は、必須ですね。
まとめ
AIの進化によって、単純な作業は自動化されていきます。
しかし、課題設定、設計、品質責任といった本質的な仕事の重要性はむしろ増えるのです。
私たちITエンジニアは、「AIを使いこなし問題解決の専門家」になっていくのです。
私たちITエンジニアは、このAIの進化という変化の波を恐るのではなく、チャンスと捉え自ら変化していくことが必要となるのです。
「コードを書くスキル」以外に、「考えるスキル」を積み上げていくことが、これからのキャリアを面白くするのです。
みなさんは、AIの進化についてどう思いますか?
ぜひ、コメントでご意見をお聞かせください。
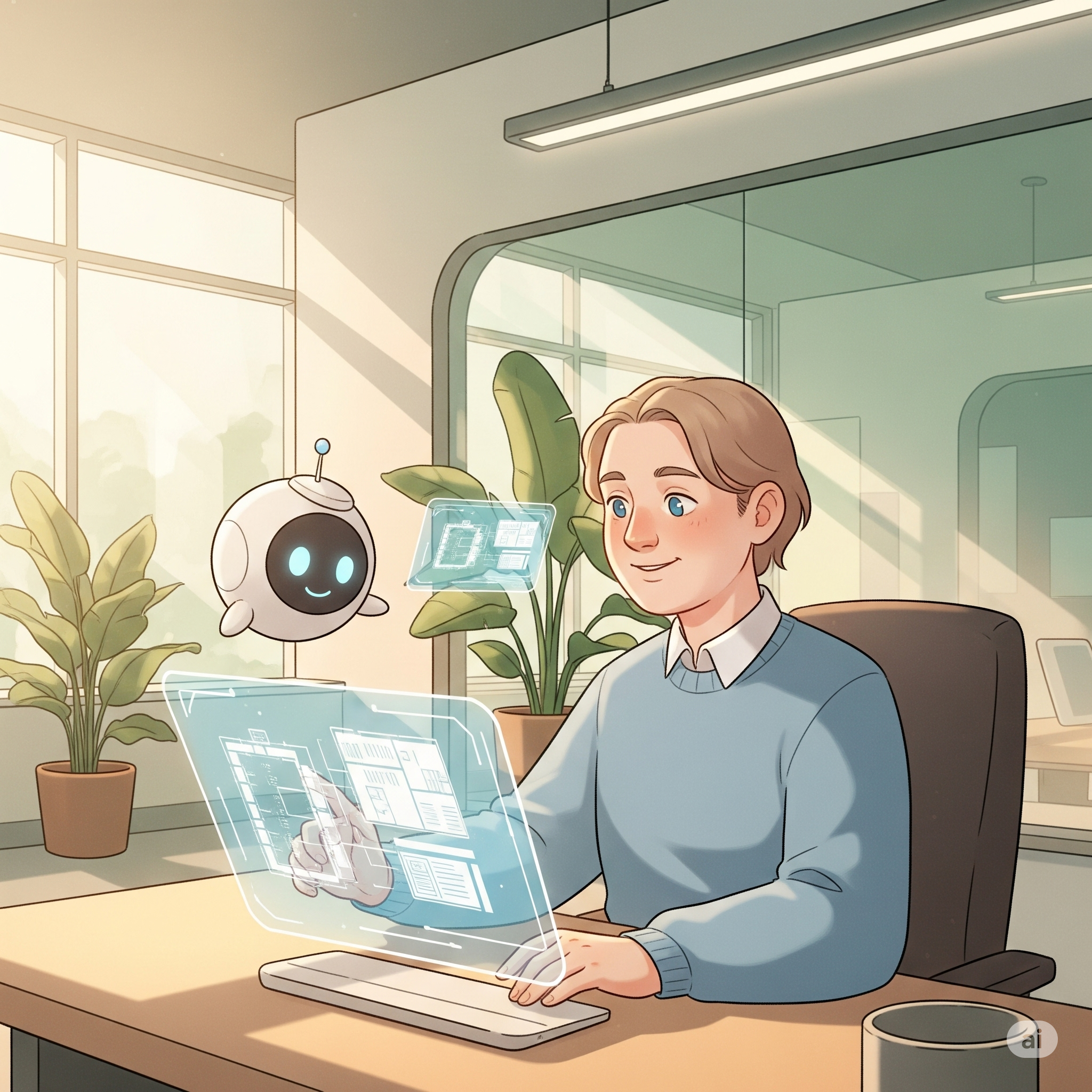


コメント